大阪・関西万博2025 宇宙未来生活ラボ – 宙(そら)に生きる未来へ (Space Living Lab- Towards Life Beyond Earth)開催のお知らせ
大阪・万博2025 宇宙未来生活ラボ Space Living Lab 宙(そら)に生きる未来へ Towards Life Beyond Earth
-
Space Living Lab 公式テーマ映像:HEXACITY – Space Station Osaka @大阪ヘルスケアパビリオン*
-
HEXACITY:Space Station Osaka – Visual Anthem for Space Living Lab @ Osaka Healthcare Pavilion*
展示イベントテーマ:ーミライの宇宙での暮らしと食ー
宇宙未来生活ラボ – 宙(そら)に生きる未来へ (Space Living Lab- Towards Life Beyond Earth
会場:大阪ヘルスケアパビリオン内「ミライの食と文化ゾーン/デモキッチンエリア」
期間:2025年8月10日(日)~16日(土)
主催:京都大学大学院総合生存学館SIC有人宇宙学研究センター
共催:鹿島建設(㈱)、DMG森精機(㈱)
協力:(一社)宙ツーリズム推進協議会 コスモ女子 宇宙ごはん研究会
宇宙服展示:岐阜医療科学大学・Amateras Space株式会社
スペースカフェ協力企業:レバンナ北海道、Amulapo (㈱)
2025年8月10日から16日まで、大阪・関西万博2025の大阪ヘルスケアパビリオン・デモキッチンにて、宇宙食に関する多彩なイベントや、宇宙や未来社会をテーマとしたイベント「宇宙未来生活ラボ – 宙(そら)に生きる未来へ (Space Living Lab- Towards Life Beyond Earth)が開催されます。会場では人工重力施設ルナグラス・ネオの模型のほか、大阪ヘキサシティの模型、そしてAmateras Space(株)および岐阜医療科学大学と共同開発中の宇宙服「VESTRA & KNIGHT SUITS」の展示も予定されています。
初日には、京都大学大学院総合生存学館教授であり、SIC有人宇宙学研究センター長の山敷庸亮氏の挨拶に続き、山崎直子宇宙飛行士からのビデオメッセージの配信を予定しています。その後、大野琢也氏(SIC特任准教授)による人工重力に関する講演が行われます。
さらに、宇宙食の紹介や、コスモ女子による宇宙食関連イベント、宙ツーリズムによる宙グルメ® 紹介、「宇宙ごはん研究会」による宇宙食の解説なども予定されています。続いて、「地球以外に人が住める惑星ってあるの?」をテーマに、月や火星、さらには太陽系外惑星への移住可能性について、分かりやすく解説します。
また、最終日の8月16日には、有人宇宙学研究センター設立メンバーであり、現在龍谷大学客員教授を務める土井隆雄宇宙飛行士の講演も予定されています。講演のスケジュールや登壇者のプロフィールについては、下記をご参照ください。
本講演は、宇宙工学、居住、健康、芸術など多様な分野の専門家によるシリーズ講演の一環として行われ、未来の宇宙生活を多角的に探求する内容となっています。
毎日開催イベント
- コスモ女子(13時〜15時)
- 宙ツーリズム推進協議会(15時~16時)
- 宇宙ごはん研究会(16時〜17時)
- 開会の挨拶(10時〜11時)
- 山敷 庸亮
- 山崎 直子(ビデオメッセージ)
- マークォート ゼルダ(司会)
- 大野 琢也(11時〜12時)
- 山敷 庸亮(17時〜18時)
- 荒木 慶一(11時〜12時)
- 桜井 誠人(17時〜18時)
- 石川 秀(11時〜12時)
- 野中 朋美(17時〜18時)
- 名倉 真紀子(11時〜12時)
- 玉根 昭一(11時〜12時)
- 深浦 希峰(17時〜18時)
- 富田 キアナ(11時〜12時)
- 藤永 嵩秋(17時〜18時)
- 萩生 翔大(11時〜12時)
- 森 裕和(17時〜18時)
- 土井 隆雄(11時〜12時)
- 日置 あつし(17時〜18時)
コスモ女子(13時〜15時)
宇宙が、もっと身近に。「コスモ女子」と学ぶ宇宙食と宇宙体験
未経験から人工衛星打ち上げを成功させた「コスモ女子」と一緒に、宇宙を味わいませんか?
各20分ずつで宇宙旅行気分を味わえる3つのプログラム
・宇宙食体験
なぜ今、宇宙なのか?
宇宙旅行時代到来の今、宇宙食について学びながら未来を体感
今とこれからの宇宙食の紹介と配布
・中学生宇宙食開発者のリアルプレゼン
日本宇宙食認定を目指す中学生の熱いプレゼンテーション
静岡のみかんゼリーを使った宇宙食体験
・地球 vs 月 謎解きチャレンジ
楽しく学べる体験型クイズで宇宙の秘密を解き明かそう
宇宙が「遠い夢」から「身近な未来」に変わる瞬間を、あなたも体験してください。
お子様から大人まで、宇宙初心者大歓迎!
宙ツーリズム推進協議会(15時~16時)
3つのプログラム(30分)の2回構成です。
ビデオと楽しいステージ発表をお楽しみください。
① 宇宙飛行士山崎直子さんとVTuberイチとのトーク(ビデオ)
いよいよ始まった宇宙旅行/宙ツーリズム®への期待と、
② 宇宙旅行の最新動向
100キロ超えのサブオービタル飛行や低軌道/ISSへの旅行、
③ 宇宙食/宙グルメ®クイズ
宇宙での食事/宙グルメ®について、“
宇宙ごはん研究会(16時〜17時)
宇宙ごはん研究会は、宇宙での食事に関して3つの視点から展示を行います。①宇宙に行くとしたらどんな食事をしたいですか?__宇宙旅行者になりきって、地上と宇宙環境での違いを学び、食べてみたい「未来の宇宙食」を考える参加型展示を行います。②宇宙で“食べる”とは?__消化や味覚など、地上では一見当たり前に思える生理現象が、宇宙環境ではどう変わるのか。科学的な視点と体験型のアプローチを通じて、宇宙での「食」と「からだ」の意外な関係を楽しみながら学べる展示を行います。③あなたは食事に豊かさを求めますか?_地球上では、栄養があれば味は気にしないという人から、味・文化的意味を求める人まで、食をめぐって様々な考え方があります。今後宇宙開発が進み、宇宙での生活が現実になれば、同じように食事に豊かさや意味を求める未来がやってくるかもしれません。「”食事っておもろいやん”を作りたい」をテーマに、具体物を用いて宇宙空間における食事について展示を行います。
8月10日(日)
開会の挨拶(10時〜11時)
山敷 庸亮
京都大学大学院総合生存学館(思修館) 教授
SIC有人宇宙学研究センター代表

山崎 直子(ビデオメッセージ)
宇宙飛行士・宙ツーリズム推進協議会アンバサダー・SIC有人宇宙学研究センター特任准教授
講演者の略歴
1999年現宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士候補
マークォート ゼルダ(司会)
大野 琢也(11時〜12時)
講演タイトル
宇宙居住には重力がいるんです
講演内容
人間の生活のためには重力が重要で、宇宙空間や月面での生活が始まった場合重力に代わるもの、遠心力を利用した人工重力が重要なインフラとなる。今回の講演では、重力が健康や食にいかにかかわっているか、人工重力施設とはどんなものかを画像を交えてわかりやすく説明します。
講演者の略歴
1991年 神戸大学 建築学科 卒
1993年 神戸大学 大学院 建築学専攻 修士
1993年 鹿島建設(株)入社 建築設計部
2021年 京都大学大学院 総合生存学館 SIC 有人宇宙学研究センター(兼)
2023年 鹿島建設(株)イノベーション推進室 宇宙担当

山敷 庸亮(17時〜18時)
講演タイトル
地球以外に人が住める惑星ってあるの?
講演内容
太陽系の中では、月・火星への移住の可能性について検討が始まっていますが、月には大気がなく、火星も大気が薄くなかなか大変ですよね。しかし宇宙には地球のような惑星がほかにもあると言われています。そのような太陽系外惑星も含めて、人が住むことができそうな惑星を紹介していきます。
講演者の略歴
京都大学工学部交通土木工学科卒(1990年)、サンパウロ大学修士(水理工学、1994年)、京都大学大学院にて博士(工学・環境地球工学専攻)取得(1999年) 。1999~2001年に国連環境計画国際環境技術センター協力企画官を務め、2001~2004年京都大学助手として勤務 。その後、日本大学理工学部講師・准教授、京都大学防災研究所准教授を経て、現在は京都大学大学院総合生存学館教授を務める 。研究分野は水資源・水環境工学、放射線影響評価、惑星環境・生命居住可能性で、福島事故後の放射性物質挙動解析や系外惑星の放射線環境評価、航空機被ばくの影響評価など。有人宇宙学・宇宙移住のための三つのコアコンセプトを2023年に出版。
8月11日(月)
荒木 慶一(11時〜12時)
講演タイトル
新しい形状記憶合金が拓く未来社会-耐震から宇宙居住まで-
講演内容
近年,我が国では,新しい形状記憶合金の材料開発と応用展開の両面で,革新的な研究開発が進んでいます。ここでは,新しい形状記憶合金の材料開発や,耐震や宇宙居住などでの応用により,どんな未来社会が切り拓けるかを紹介します。
講演者の略歴
荒木慶一 京都大学・教授
1998 京都大学・博士(工学)の学位を取得
1998-2000 米国イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で研究員
2000-2018 京都大学・助手,准教授
2018-2024 名古屋大学・教授
2024- 現職

桜井 誠人(17時〜18時)
講演タイトル
宇宙で生きる!宇宙居住と物質循環
講演内容
人類は地球低軌道から月軌道へと生存圏を拡大しようとしています。人間は一日に600リットル程度の酸素を呼吸し、同体積程度の二酸化炭素を排出しています。水は一日2.5リットルほど飲料しています。酸素製造、二酸化炭素除去、空気再生など人間が生存できる環境を維持するシステムは環境制御・生命維持システム(ECLSS(イークルス): Environmental Controll Life Support System)と呼ばれています。生命維持の根幹である水と空気、および廃棄物処理などに関して物質循環の観点からご紹介します。
講演者の略歴
1996年 早稲田大学理工学研究科応用化学専攻 博士課程修了
1998年 日本学術振興会海外特別研究員(ドイツブレーメン大学)
2000年 東京女子医科大学 医用工学研究施設 助手
2001年 航空宇宙技術研究所 入所
2003年 宇宙航空研究開発機構(上記改編)

8月12日(火)
石川 秀(11時〜12時)
講演タイトル
月でポテトは揚がるのか? ~宇宙の暮らしと、地球の未来を考えよう~
講演内容
宇宙はどんなところだろう? 地球と何がちがうのだろう? なぜ、宇宙に行くのだろう? 宇宙は「?」だらけです。いま、宇宙で生活する時代が始まろうとしています。「月でポテトは揚がるのか?」そんな身近な話題を交えて “宇宙生活” を一緒に考えませんか?
講演者の略歴
鹿島建設(株)エンジニアリング事業本部に勤務。関西大学大学院を卒業。博士(工学)。
2022年にJAXAの研究開発プログラムに参加。専門は殺菌、微生物制御工学。

野中 朋美(17時〜18時)
講演タイトル
宇宙で心地よく暮らす時代へ:快適ECLSSが描く未来のライフスタイル
― 一般民間人宇宙旅行を見据えた新しい宇宙居住のかたち ―
講演内容
2040年代には年間約1万人の一般民間人が宇宙を訪れる時代が到来すると予測されています。本講演では、従来の環境制御・生命維持技術ECLSS(エクルス)に「快適性」と「人間中心設計」の視点を加えた快適ECLSSの構想と実践例を紹介します。宇宙空間におけるQOL(生活の質)の向上を目指し、地上の技術・文化と接続した新たなライフスタイルの可能性を議論します。
講演者の略歴
専門は経営システム工学、サービス工学。博士(システムエンジニアリング学)。慶應義塾大学環境情報学部卒業、企業で検索エンジンマーケティングに従事した後、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)修士課程・博士後期課程に1期生として入学し4年間で早期修了。SDMでは、デルフト工科大学やスイス連邦工科大学への研究科派遣留学や、MITに研究インターンシップ滞在。神戸大学大学院システム情報学研究科特命助教、青山学院大学理工学部経営システム工学科助教、立命館大学食マネジメント学部准教授・立命館EDGE+R副総括責任者などを経て2023年4月より早稲田大学創造理工学部経営システム工学科教授。持続可能なビジネス・社会システム研究、一般民間人宇宙滞在のための快適ECLSS、働きがいや生産性などの人の情報を起点としたサービス生産システム設計に従事。文部科学省国立研究開発法人審議会臨時委員(宇宙航空研究開発機構部会)、内閣府クールジャパン・アカデミアフォーラム構成員、尾道市ウェルビーイング政策アドバイザー、IFIP WG5.7 member、日本経営工学会理事、日本創造学会理事、サービス学会理事などを務める。

8月13日(水)
名倉 真紀子(11時〜12時)
講演タイトル
宇宙でのより良い暮らしのために
講演内容
宇宙の暮らしはどんなものになるでしょうか?
今の宇宙と地球の暮らしを比べて、理想の宇宙居住に必要なものを一緒に考えます。
講演者の略歴
2004年 名古屋大学 工学部 社会環境工学科 卒業
2006年 名古屋大学大学院 環境学研究科 都市環境学専攻 修士課程 修了
2006年 鹿島建設(株) 入社 建築設計本部 配属
2009年~現在 鹿島建設(株) 関西支店 建築設計部 勤務
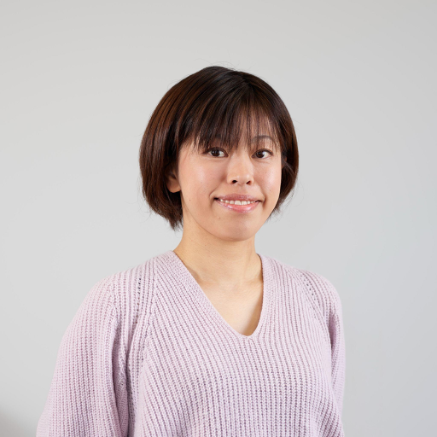
玉根 昭一(11時〜12時)
講演タイトル
宇宙でのより良い暮らしのために
講演内容
宇宙の暮らしはどんなものになるでしょうか?
今の宇宙と地球の暮らしを比べて、理想の宇宙居住に必要なものを一緒に考えます。
講演者の略歴
1985年 日本大学工学部建築学科 卒業
1985年 積水ハウス(株) 入社 宇都宮営業所設計課 配属
2022年 宇都宮大学大学院工学研究科博士後期課程修了 博士(工学)
2023年 積水ハウス(株) 総合住宅研究所 環境技術研究開発グループ
専門は住まいの光視環境、宇宙居住の基礎研究

深浦 希峰(17時〜18時)
講演タイトル
月面開発の最新動向と民間企業参入の黎明期
~月面社会実現に向けた食、住、インフラ開発~
講演内容
月面社会実現に向けたインフラ、というとどのようなものを思い浮かべるでしょうか。それは、地球-月面/月面-月面での通信インフラ、人の生活を実現する食・居住インフラ、輸送(ロケット/離発着機)に不可欠なエネルギー(燃料)インフラなど非常に多岐に渡ります。
本講演では、日揮グローバルの取り組む案件をベースにその開発の一端をご紹介致します。
講演者の略歴
2015年、日揮株式会社(現日揮ホールディングス)入社。
プラントエンジニアとしてLNGプラントやガス処理プラントなど、海外プロジェクトの設計業務に従事。
2018年、社内で宇宙ビジネスを構想する有志活動を開始。
2020年に専任チーム「月面プラントユニット」立ち上げ。
JAXAとの「月面推薬生成プラント構想検討に係る連携協力協定」締結。
2021年~2023年、2年間のJAXA有人宇宙技術部門への出向を経て現職。
月面・月近傍の経済圏創出へ向け「インフラ」という切り口で事業創出、産学連携に尽力する。
宇宙ビジネスコンテスト「IBARAKI Next Space Pitch #2, #3, #4」審査員
経産省「始動Next Innovator」プログラム6期
鳥取県主催「第2回星取件宇宙ビジネスコンテスト」最優秀賞
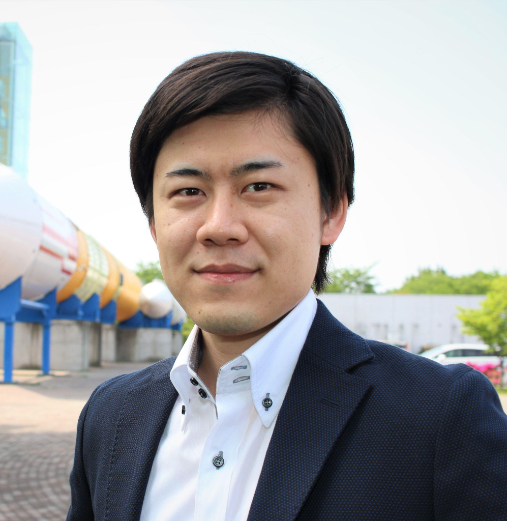
8月14日(木)
富田 キアナ(11時〜12時)
講演タイトル
災害食と宇宙食
講演内容
災害時の食事って、大変困ります。調理器具がなく、冷蔵庫もなく、それでいて必要な栄養を満たさねばなりません。そのため缶詰、お湯をいれなくても食べられる麺類などあります。宇宙食も災害食との共通点があります。例えば火が使えない、長期間保存しておかねばならない、調理ができない、などなど。災害食を学んで、宇宙につなげましょう。
講演者の略歴
英国で2つの修士号 (2019年エジンバラ大学、2020年ケンブリッジ大学)を取得。
2021年京都大学大学院博士課程に入学し、現在に至る。
新刊「有人宇宙学:宇宙移住のための3つのコアコンセプト」ではコラムを担当。
宇宙飛行士の山崎直子さんにインタビューを行い、宇宙でのリーダーシップを考察し執筆。

藤永 嵩秋(17時〜18時)
講演タイトル
Space Diving 疑似1/6重力を体感する水中疑似月面プログラム
講演内容
語り聞かされる宇宙ではなく、自分の身体で感じ取る。
NASAで実施されている宇宙飛行士の水中訓練をベースとし、水中を月面に模したレクリエーションコースについてお話しします。
海から見上げる宇宙との深い繋がりにも触れてまいります。
講演者の略歴
AquaNaut代表
株式会社エコ・プラン(管工事一級施工管理技士、第一種電気工事士)
PADIマスタースクーバダイバートレーナー
山口県下関市出身。旧:都立三鷹高等学校卒業。中央大学卒業。
元:学生YMCA所属。2013年タオ島にて初級ライセンス取得。
本業の傍ら、海×宇宙をテーマに2019年よりプロダイバーとなる。
JAXA宇宙飛行士選抜試験にも挑み、文系出身者としてNHK・日テレ出演。JAXA英語試験まで突破。
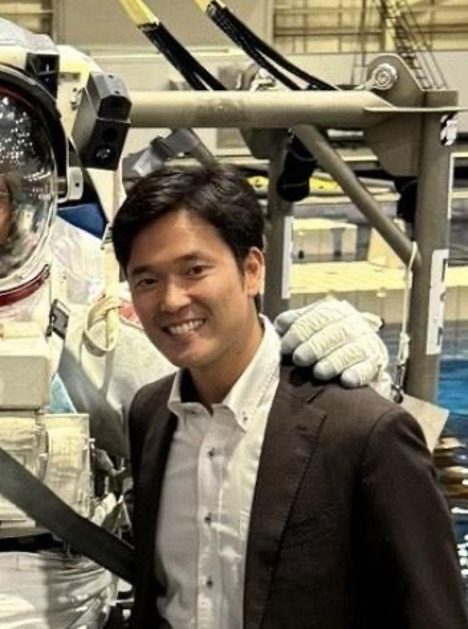
8月15日(金)
萩生 翔大(11時〜12時)
講演タイトル
動く身体を捉えなおす ―宇宙から考える運動と健康―
講演内容
私たちは日々、当たり前のように地球の重力の中で身体を動かしていますが、重力がほとんど作用しない宇宙では、身体や動きのあり方は大きく変化します。本講演では、宇宙飛行士の運動測定を含む最前線の研究を手がかりに、「動く」とは何かを根本から捉えなおします。そして、こうした知見が、私たちの暮らしや健康、さらには高齢化社会の課題とどのように関わってくるのかを、一緒に考えていきます。
講演者の略歴
2011年、京都大学総合人間学部卒業。2016年、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程を修了し、人間・環境学博士の学位を取得。2016年から2019年まで東京大学大学院教育学研究科にて特任研究員を務めた後、2020年より京都大学大学院人間・環境学研究科講師を経て2022年より現職。動きの仕組みを調べる実験や数値解析を通して、「ヒトはどのようにして身体を動かしているのか?」という問いに取り組んでいる。
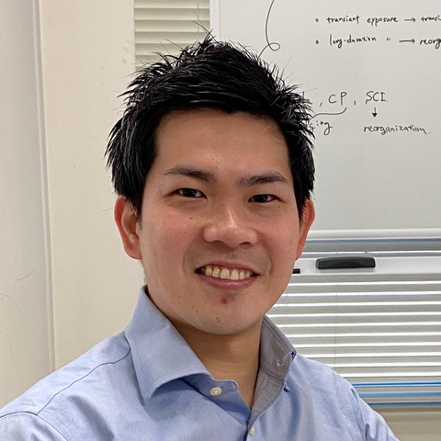
森 裕和(17時〜18時)
講演タイトル
宇宙産業のトレンドと注目テック!
講演内容
近年話題に上がる宇宙ビジネスをわかりやすくまとめ、世界中を飛び回る講演者がグローバルで注目の面白い宇宙テックを紹介!
講演者の略歴
・宇宙ビジネスコンサルタント
・Caelum Consilium株式会社代表取締役
・一般社団法人SPACETIDE CXOアドバイザー
・Warpspaceグループ最高戦略責任者兼Warpspace USA CEO
宇宙ビジネス・コンサルタントとして国内外の政府や宇宙関連大企業のコンサルティングに従事する傍ら、国内外の企業や団体の役員、理事、顧問を歴任。 エジンバラ大学で理論宇宙物理学を専攻し、飛級入学かつ首席で卒業。世界3周(100カ国以上訪問)、プロダイバーなど

8月16日(土)
土井 隆雄(11時〜12時)
講演タイトル
有人宇宙活動
講演内容
1961年ガガーリンによる人類初の有人宇宙飛行以来、宇宙は人類にとっての進出可能な新世界となった。日本の『第一期有人宇宙活動』は、1985年に国際宇宙ステーション計画への参加決定及び第一次材料実験に参加する日本人宇宙飛行士の選抜により始まった。日本は短期有人宇宙ミッションを通して、宇宙実験技術、ロボットアーム操作技術、船外活動技術など有人宇宙活動に必須な技術を獲得した。『第二期有人宇宙活動』は、2008年「きぼう」日本実験棟を宇宙ステーションに取り付けるミッションを契機に始まった。日本人宇宙飛行士による長期ミッションが開始され、宇宙飛行士訓練、有人宇宙施設の運用、宇宙貨物船の飛行などの技術を獲得した。日本そして世界の有人宇宙活動は何をめざし、私たちはどこに行こうとしているのだろうか。
講演者の略歴
1954年、東京生まれ
1983年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了
2004年、ライス大学大学院博士課程修了
工学・理学博士
1997年、スペースシャトル「コロンビア号」に搭乗し、日本人として初めての船外活動を行う。2008年、スペースシャトル「エンデバー号」に搭乗。ロボットアームを操作し、日本初の有人宇宙施設「きぼう」日本実験棟船内保管室を国際宇宙ステーションに取り付ける。2009年から2016年にかけて、国連宇宙部で国連宇宙応用専門官として宇宙科学技術の啓蒙普及活動に取り組む。2016年4月より京都大学宇宙総合学研究ユニット特定教授に就任。2020年4月より京都大学大学院総合生存学館(思修館)特任教授、2020年7月より特定教授。2002年と2007年には超新星を発見する。

日置 あつし(17時〜18時)
講演タイトル
宇宙の劇場 重力から解放された自分の体の可能性って!?
講演内容
世界各地で踊ってきたアーティストが、たどり着いた「宇宙の無重量劇場」。それを想像しながら皆さんと一緒に、宇宙での芸術についてパフォーマンスも交えながら考えてみたいと思います。特別生演奏とのコラボレーション予定。
講演者の略歴
京都市出身 無重量状態の「宇宙の劇場」を構想しているアーティスト。コンテンポラリーダンス&日本舞踊等の公演で13カ国ほどにて作品上演とパフォーマンスを行う。JR京都伊勢丹創業祭メインビジュアルアーティストや京都府アーツアドバイザーを務め、国際フェスティバルの主催や運営、現代音楽、インスタレーション、茶道など様々な分野での活動や、地元では吉田剣鉾保存会(京都市無形民俗文化財)にて地域文化への貢献も行う。京都市市民憲章奨励者。宿曜経アドバイザー。MPD事業構想修士。

*HEXACITY – Osaka Space Station Concept
HEXATRACK-Space Express Concept, designed and created by Yosuke A. Yamashiki, SIC Human Spaceology Center, GSAIS, Kyoto University
HEXACITY-HEXATRACK Earth Station Concept, designed and created byJuniya Okamoto & Yosuke A. Yamashiki
Geo Glass, a hypergravity facility on the Earth for spacetravel training, concept by Takuya Ono, designed by Juniya Okamura, and coordinated by Yosuke A. Yamashiki
All Visual Effect and detailed design of above contents are generated by Juniya Okamura
Music ”Osaka Space Track”composed by Yosuke Alexandre Yamashiki
This post is also available in:
 English (英語)
English (英語)

